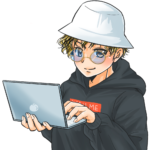
こんにちは!資格学校運営者のぽんです🦍 X(旧Twitter):@ponchan_golf
今回は、宅建業法を最短でマスターする方法をまとめました!
✅ はじめに:なぜ宅建業法は“最優先”でマスターすべきなのか?
宅建試験で最も配点が高いのが「宅建業法」です。全50問中20問、つまり3分の1以上がこの分野から出題されます。以前の記事にも投稿しましたが、合格ラインが35点前後とされている宅建試験において、”業法を取れれば合格に大きく近づける”ということです。
📊 1. 宅建業法の出題傾向を知ろう
◆ 出題数と配点
| 分野 | 出題数 | ー |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 | ー |
| 権利関係(民法など) | 14問 | ー |
| 法令上の制限 | 8問 | ー |
| 税・その他 | 8問 | ー |
◆ 主な出題項目
- 宅地建物取引業の定義(取引・宅建業の意味)
- 宅建業の免許制度(名義貸し禁止、免許の拒否、欠格事由)
- 事務所・従業者関係(宅建士の設置義務、宅建士証の掲示義務)
- 営業保証金と保証協会(供託金、金額、還付など)
- 業務上の規制(誇大広告の禁止、クーリング・オフ制度、手付金20%以内)
- 重要事項説明(35条書面)
- 契約締結時の書面(37条書面)
- 報酬(仲介手数料)の制限
- 監督・指導・処分
- 罰則と行政処分の関連
- その他・頻出項目
◆ 出題形式の特徴
- 語尾の違いを問う問題が多い(〜できる/〜しなければならない)
- 数字・割合・日数の正確な記憶を要求
- 選択肢がまぎらわしく、正確な理解が重要
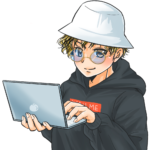
なので問題に正解しているかではなく、選択肢を正確に理解している事が最も
大事になります!
📝 2. 宅建業法を最短でマスターする5ステップ勉強法
▶ ステップ①:全体像を把握する(インプット)
まずは「宅建業法とは何か」をざっくり把握しましょう。
おすすめは図解入りのテキストやYouTube講義です。僕は暗記系に関して、基本Youtubeを観て
覚えることにしました。テキストを一から読んでというよりは、具体的に分からない内容を調べる為に
テキストは使用してましたね!!
僕が過去に視聴していたYoutubeチャンネルは
・棚田の不動産大学 youtube.com/channel/UC2tunZXxelGam73VcK3E-ug
・吉野塾 https://yoshinojuku.stores.jp/
この辺りが僕自身としては凄くわかりやすかったですね!他にもチャンネルはありましたが、高額&期限付き(1年)で買い取りではないなど制限がありますので、お金を支払う時は要注意です!!
どこまで無料、有料でやるかの判断が大事ですが、項目ごとで数百円の参考資料などがWeb購入できたりするので、そちらもおすすめですね!僕は模試と自分の苦手な分野の所だけ購入しました!
Youtubeのリンクも貼り付けさせていただきましたので、是非ご参考ください!
▶ ステップ②:過去問で頻出論点を把握する
- 直近3〜5年分を中心に演習
- 1問1答形式で細切れ学習もおすすめ
- 選択肢ごとの正誤を判断できるまで繰り返す
- テキスト⇔問題集を繰り返し行い、分野毎で進める
この辺りの合う合わないは人それぞれなのでやり方は自由ですが、基本的なやり方としてはこのやり方が一番合いました。
▶ ステップ③:数字・語句を“意味ごと”暗記
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| クーリングオフ期間 | 8日間 |
| 免許の更新 | 5年ごと |
| 手付金の上限 | 代金の20%以内 |
これ以外にも数字関連は沢山出てきますので、”毎日少しずつ暗記する”事で記憶が定着していきます。
その日覚えても次の日には半分以上忘れています。皆さん、意外と覚えた気分になり、一度覚えたら
暫く手を付けなくて、3割しか覚えていない・・・みたいな事があると思います。
これは全員に共通することですので、ご安心くださいw
ですので ”毎日” ”継続的に” ”繰り返し” やる事で、記憶が定着していくので、是非試してみて
下さい!!
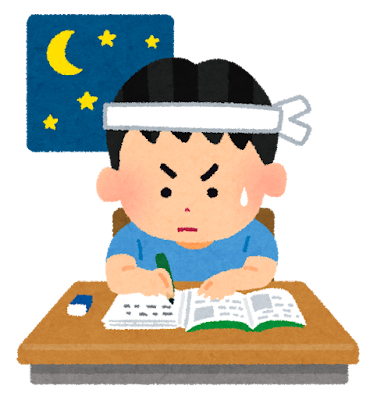
▶ ステップ④:ひっかけ問題に慣れる
- 「〜できる」「〜しなければならない」など語尾の違いに注意
- 似た用語の使い分けを徹底
- 問題文を丁寧に読む習慣をつける
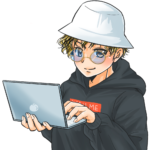
この辺りは問題を解くときのコツやから”これ!”っていうのはあまり無いけど
結構基本になる部分!
【第1問】
宅建業者は、広告を出す際、取引態様(自ら売主・代理・媒介)を表示することについて正しいものはどれか。
A. 広告主の判断で任意に表示することができる
B. 表示は努力義務であり、違反しても罰則はない
C. 必ず表示しなければならない
D. 契約締結時にのみ表示すればよい
正解:C
解説:
広告では**取引態様の明示は義務(しなければならない)**です。
「できる」や「努める」ではなく、法的義務+罰則あり。
▶ ステップ⑤:反復学習で定着させる
- 毎日少しでも復習の時間をとる
- カード学習やアプリで記憶を強化
- 時間制限付きの模試で実戦力を養う
💡 3. 宅建業法を得点源にする3つのコツ
✔ コツ①:数字は語呂で覚える
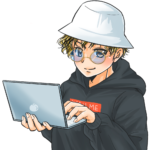
色んな語呂合わせがあるから色々見てみるといいよー!!
自分が覚えやすいようなものもあるから笑
■手付金の保全措置・上限
- 規定内容:
- 自ら売主の場合、手付金は代金の20%以内
- 10%以上受け取る場合は保全措置が必要
語呂合わせ:
「い(1)じゅう(0)ふた(2)まる」
→ 10%以上・20%以内
(=10%を超えたら保全、20%が上限)
■営業保証金(供託額)
- 金額:
- 主たる事務所:1,000万円
- 従たる事務所:500万円
語呂合わせ:
「いちご(1・5)事務所」
→ 1,000万円と500万円を覚える
✔ コツ②:問題の“型”を覚える
- 35条と37条の違い
- 免許が不要な取引
- 報酬の限度額とその内訳
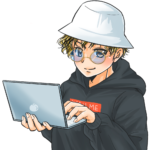
この辺りの問題は結構出てくるポイントですね!!
問題を解く時は意識して解いてみて下さい!
【第1問】
・宅建業者が売主となる宅地売買契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A. 35条書面は、契約締結後に交付してもよい
B. 37条書面は、契約締結前に宅建士が説明しなければならない
C. 35条書面は、宅建士が記名押印した上で、契約締結前に説明しなければならない
D. 37条書面は、宅建士の記名押印は不要である
正解:C
解説:
- 35条書面(重要事項説明書)
- 契約締結前に交付+宅建士が口頭で説明
- 宅建士の記名押印が必要
- 37条書面(契約書面)
- 契約締結後に交付
- 宅建士の記名押印も必要(説明は不要)
【第2問】
次のうち、37条書面に記載されるが、35条書面には記載されない項目はどれか。
A. 代金の額、支払い時期・方法
B. 登記簿上の権利関係
C. 建築基準法上の制限内容
D. 私道負担の有無
正解:A
解説:
- 35条書面(契約前)…物件や権利、法令制限などの“説明中心”
- 37条書面(契約後)…契約条件(代金・支払時期・引渡日など)中心
→代金や支払条件は契約内容なので37条書面のみ。
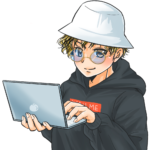
こういった細かい所の違いが沢山出てくるので、是非参考にしてみて下さい!
📚 4. 宅建業法の勉強におすすめ教材
📕 テキスト
- 『みんなが欲しかった宅建士の教科書』(TAC)
- 『パーフェクト宅建士』(住宅新報社)
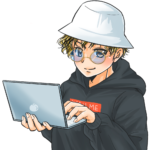
僕のは他の記事にも貼り付けてますが、テキスト・過去問はこちらですねー!
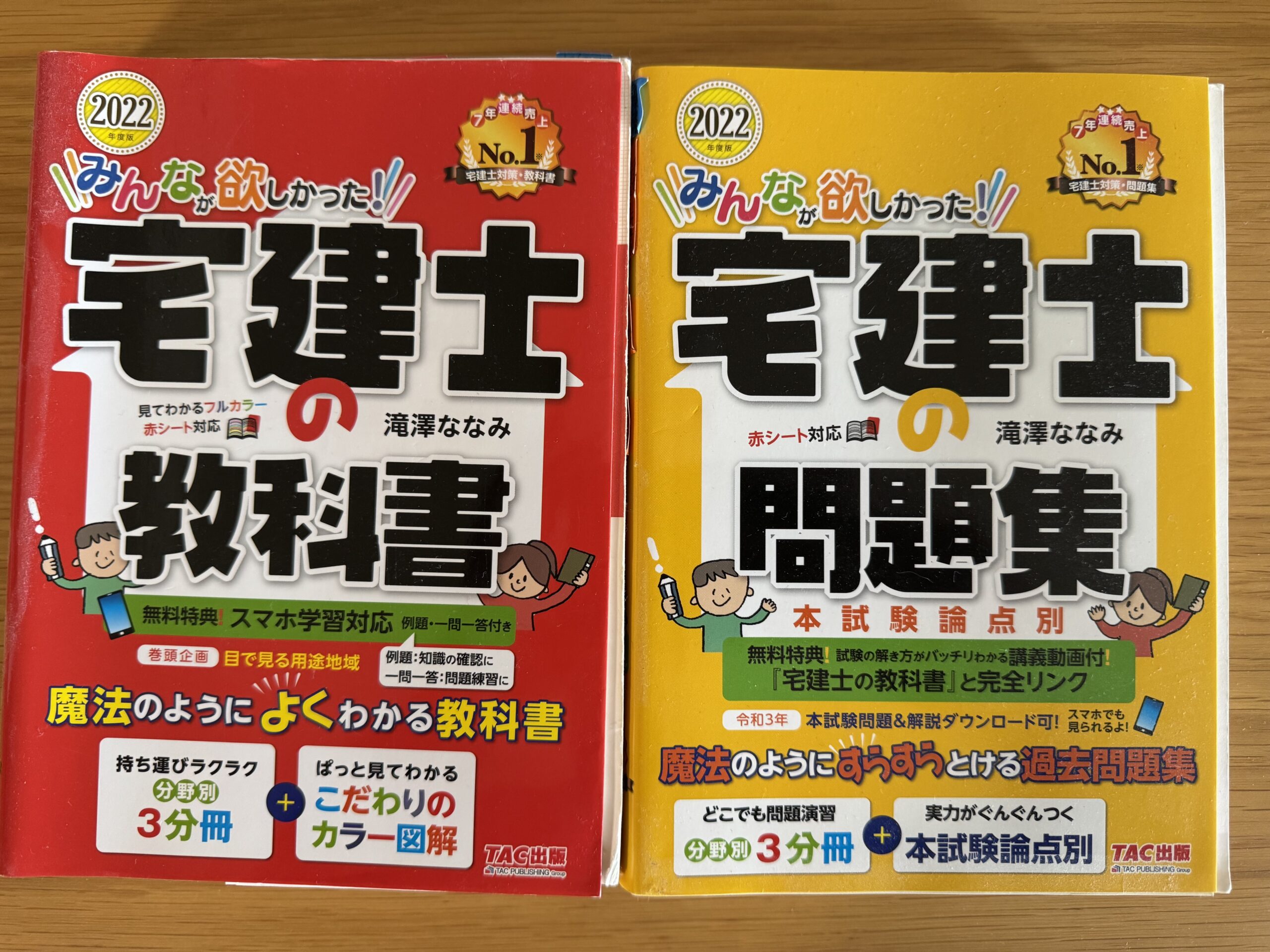
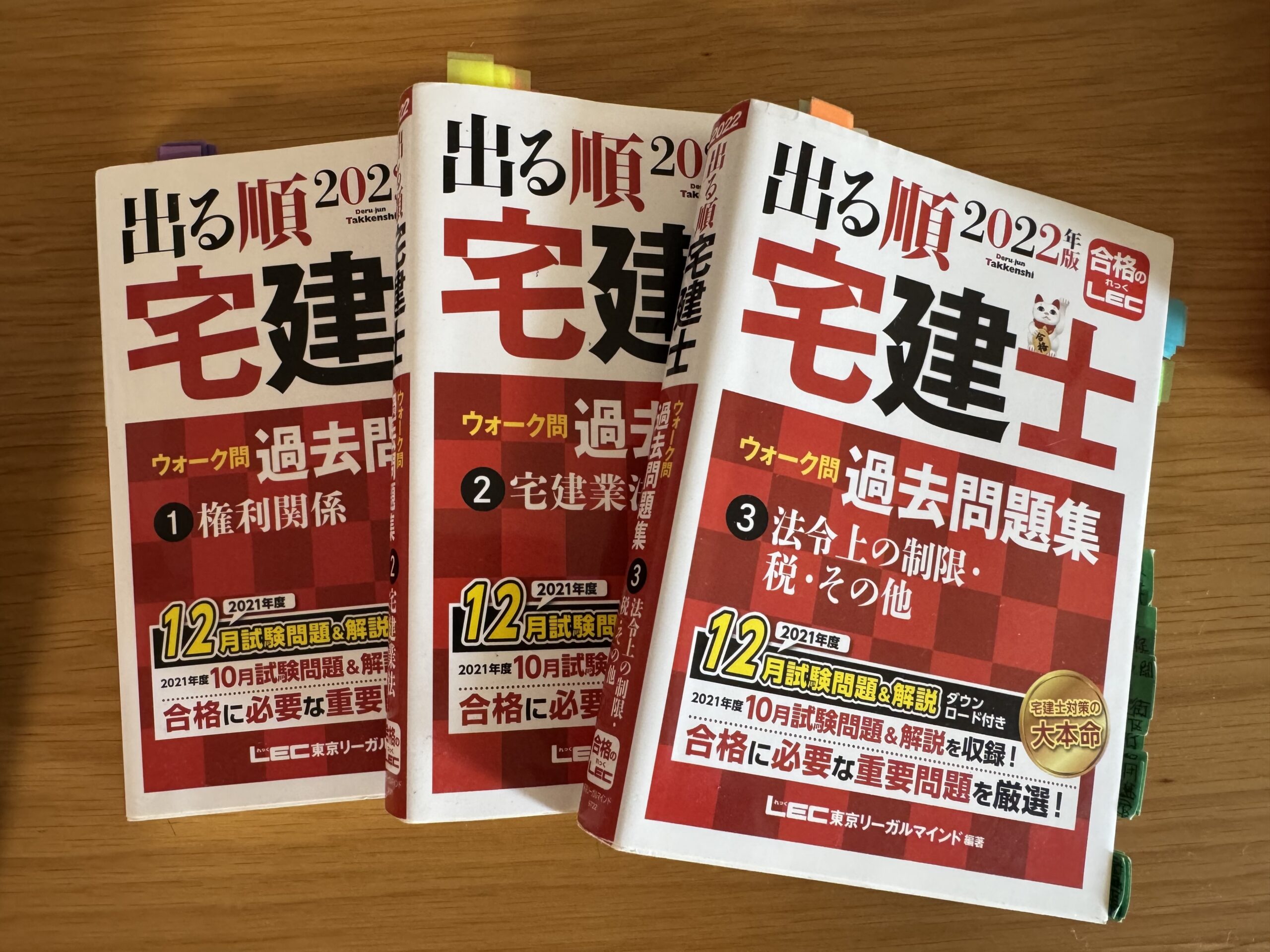
🏁 まとめ
宅建業法は、配点が高く、暗記中心で短期間でも仕上げやすい分野です!!
最初にここを攻略しておけば、他の難関分野にも時間をかけられ、合格率がグッと上がります。
ちなみに民法・権利関係は難易度が高くみなさんが苦労する部分だと思います・・・
宅建業法は点数が一番取りやすく一番差がつくパートなので、確実に1点ずつ積み重ねて
行きましょう!!
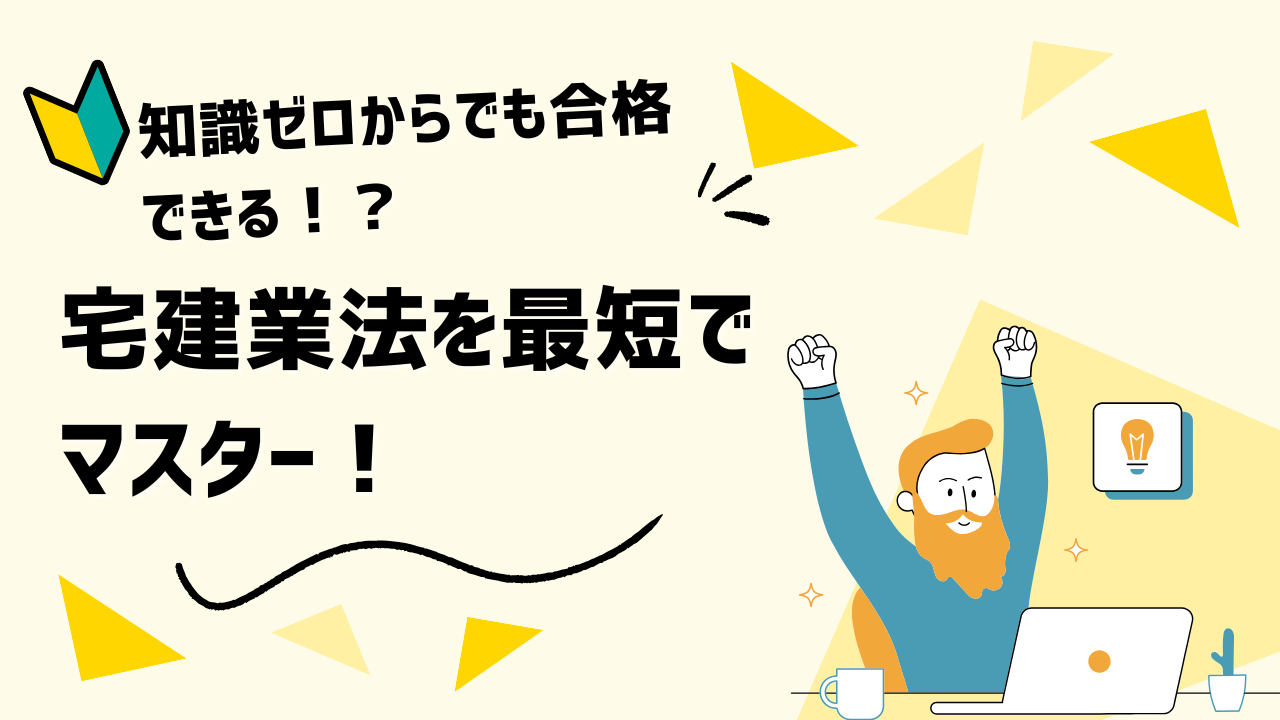
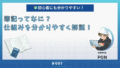
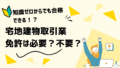
コメント