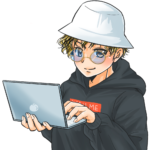
ぽん
こんにちは!資格学校運営者のぽんです!🦍 X(旧Twitter):@ponchan_golf
まずは宅建業法を一から説明していくでー!!

ゴリくん
うん、まずは宅建業法から極めていきたいねんなー!!
宅地建物取引業(宅建業)は、不動産取引を行う上で必ず押さえておくべき基本概念です!
宅建試験でも毎年出題される分野であり、実務でも免許の有無が大きく関係します。
この記事では、法律上の定義から免許が必要なケース・不要なケースまで具体例を交えて解説します。
1. 宅地建物取引業の法律上の定義
宅地建物取引業法第2条によると、宅建業とは次のように定義されています。
宅地または建物について、他人のために売買・交換・貸借の代理または媒介を行う行為、
または自ら売買または交換を行う行為を、業として行うこと。
つまり以下の3つをすべて満たす場合に「宅地建物取引業」に該当します。
- 取引対象物:宅地または建物
- 行為の種類:売買・交換・貸借の代理または媒介、自ら売買・交換
- 業として行う:反復継続して行う意思(営利目的が基本)
2. 取引対象物の範囲
宅地とは?
- 建物が建っている土地
- 建築予定の土地(造成中や更地を含む)
- 都市計画区域外でも建築可能な土地
ちなみに宅地にならない場所はこんな所!!
道路、公園、河川、広場、水路、農地、山林、工業専用地域
※農地や山林でも、建築予定があれば宅地扱いになります。
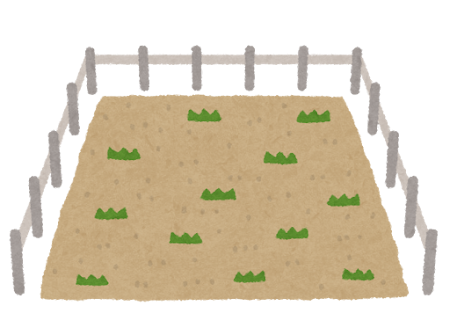
建物とは?
- 屋根・柱・壁を備えた不動産で、土地に定着しているもの
- 登記の対象となるもの(プレハブでも基礎固定型なら該当)

3. 行為の種類:売買・交換・貸借
- 売買:金銭と引き換えに所有権を移転する契約
- 交換:不動産同士や不動産と動産の交換契約
- 貸借:賃貸借契約や使用貸借契約など
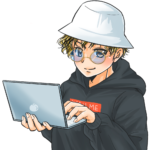
ぽん
この辺はあんまり勘違いすることも無いし、すぐ分かる内容やから大丈夫かな!
4. 代理と媒介の違い
| 代理 | 媒介 |
|---|---|
| 依頼者の名義で契約を締結する | 売主と買主の間を取り持つ |
| 契約当事者となる | 契約当事者にはならない |
5. 「業として」と判断される基準
宅建業法における「業として」とは、次のような場合を指します。
- 反復継続して取引を行う意思がある
- 営利目的で行う(法人・個人問わず)
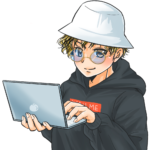
ぽん
これは宅建業者が基本的に当てはまる事になる!
試験でもよく出てくる内容やからこの辺はしっかり判断できるようになっといた方が良いな!
試験でよく出る“業として”の事例
| 事例 | 宅建業にあたる? | 理由 |
|---|---|---|
| 自分が所有する宅地を、生活費のために1回だけ売却 | ❌ あたらない | 反復継続性なし |
| 所有地を分譲して、年に数回売却を繰り返す | ✅ あたる | 反復継続+利益目的 |
| 他人の土地を頼まれて1回だけ売却の媒介をする(報酬なし) | ❌ あたらない | 報酬なし+反復継続性なし |
| 他人の土地売却を年に何度も媒介して報酬を得る | ✅ あたる | 反復継続+報酬あり |
| 建売住宅を毎年5棟販売する建設会社 | ✅ あたる | 宅地建物取引業そのもの |
| マンション管理会社が入居者募集を1回だけ代行 | ❌ あたらない | 反復継続性なし |
| 不動産会社の社員が副業で何度も物件仲介 | ✅ あたる | 個人でも反復継続+利益目的あれば該当 |
一覧にしてるから是非参考にしてみて下さい!
免許が不要なケース
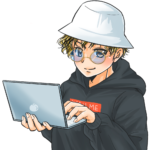
ぽん
この辺りも試験に出るから具体例を一覧にまとめてみたでー!
今の知識を確認してみてや!
| 事例 | 宅建業にあたる? | 理由 |
|---|---|---|
| 自分が所有する宅地を自分で売る(生活費のため1回だけ) | ❌ あたらない | 反復継続性なし |
| 自分の賃貸マンションを自分で貸す | ❌ あたらない | 自己所有物件の賃貸は免許不要 |
| 国や自治体が所有地を売却 | ❌ あたらない | 公共団体は免許不要 |
| 信託銀行が信託財産としての土地を売却 | ❌ あたらない | 信託業務として行う場合は免許不要 |
| 弁護士が依頼を受けて不動産売買を1回行う | ❌ あたらない | 弁護士業務の範囲内であれば免許不要 |
| 銀行が担保不動産を競売で売却 | ❌ あたらない | 金融機関の担保権実行は免許不要 |
| 不動産会社が自社所有地を販売(年1回だけ) | ❌ あたらない | 反復継続性がなければ免許不要 |
まとめ
宅地建物取引業の定義は、宅地または建物+取引行為+業として行うの3要件がポイントです。
特に「業として」の判断や対象物の範囲は試験でも狙われやすい部分です。
免許が必要かどうか迷うケースも多いため、実務では必ず確認しましょう。
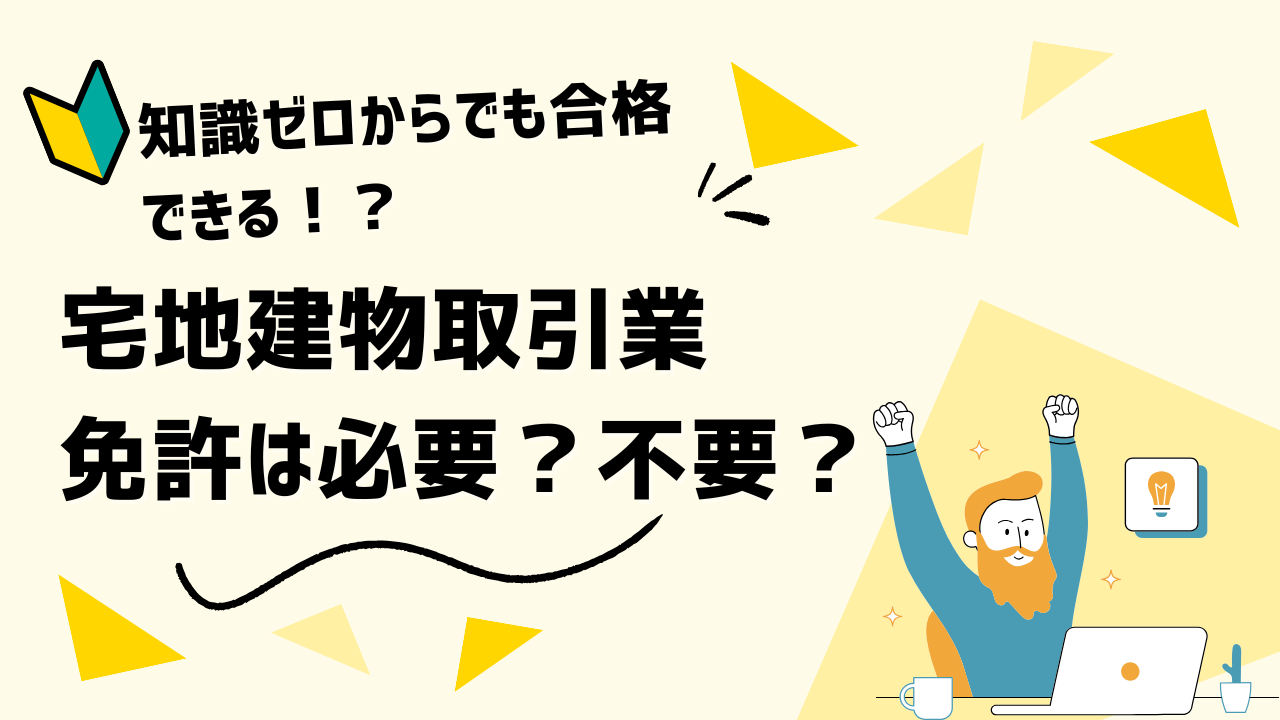
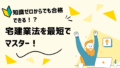
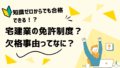
コメント